初めて級を調べる人や伸び悩んでいる人、どこから手をつければいいか迷いますよね。
級ごとの難易度や必要な練習量が分かりにくく、目標設定が曖昧になりがちです。
この記事ではボルダリング級の目安を10級から二段まで丁寧に解説し、到達までの月数目安や1セッションの時間、頻度、休息の取り方まで具体的に示します。
さらに級別に効くトレーニングメニューやジムと外岩で生じる級差の要因、次の目標級の決め方も実践的に紹介します。
まずは自分の現在の級に合う章から読み進めて、無駄のない練習計画を一緒に作りましょう。
ボルダリング級の目安と難易度一覧
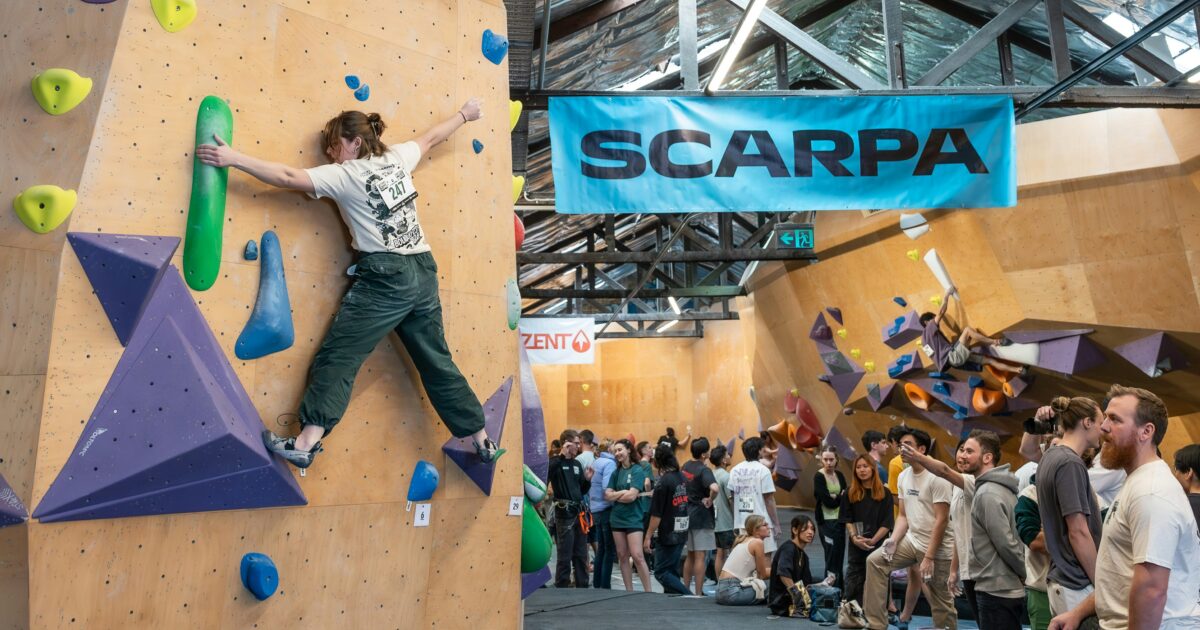
ここでは日本の一般的なボルダリング等級を、初心者向けの目安から上級者向けの到達感まで分かりやすく解説します。
各級で求められる動きや課題の特徴を押さえれば、次に狙うべき目標が明確になります。
10級
大きなホールドを使う直立の壁が中心で、初心者や子どもが登る最初の一歩に適しています。
足をしっかり使うことと、手でしっかりホールドを掴む安心感を身につける段階です。
9級
ホールドはまだ取りやすく、ムーブは単純で直線的な動きが多いです。
バランスの取り方や足の置き方を覚える練習に最適で、登る回数で上達を感じやすいです。
8級
サイズの小さいホールドや少し傾いた壁が出てきて、体の使い方が問われるようになります。
手だけに頼らず、足の精度と重心の移動を意識することが重要です。
7級
ホールドの形や配置に工夫が増え、バランスを崩さずに体を返す技術が求められます。
端的な力だけでなく、体重移動やフットワークの練習が効果を発揮します。
6級
小さな縁や浅いポケットが登場し、指先の使い方と保持力が必要になります。
リーチの工夫や、ムーブをつなげるためのテンポ配分も学ぶべき点です。
5級
パワーとテクニックの両方が問われる段階で、斜面やスローパーが増えてきます。
ムーブのバリエーションが広がるため、課題ごとにアプローチを変える柔軟性が求められます。
- フットワーク精度
- スローパー保持練習
- ヒールフックの基礎
- ダイナミックムーブ入門
4級
テクニカルなムーブが増え、体幹と柔軟性の両方が活きる課題が多くなります。
効率的な動きと、次の一手を考える洞察力で差がつきます。
3級
複雑なシーケンスや小さなホールドの連続が増え、総合力が試される段階です。
以下は3級で求められる代表的なポイントです。
| 特徴 | 目安 |
|---|---|
| ムーブ | 複雑な連続技 |
| 保持力 | 中程度から高強度 |
| 体幹 | 高い安定性 |
2級
前腕の保持力や指の強さがより重要になり、核心での一手が勝負を分けます。
壁の変化に対応する判断力と、限界近い力を出し切る経験が必要になります。
1級
高いテクニックと強い指力を求められる、上級者向けの難易度です。
細かい足位置や体の捻りを駆使して、難しいホールドをつないでいく力が求められます。
初段
ジムで上位に位置するレベルで、課題はしばしば持久力と瞬発力を同時に要求します。
ムーブの合理化とリハーサルで登る精度を高める必要があります。
二段
アマチュアの上限に近い難易度で、細いホールドや斜めの壁での高強度ムーブが連続します。
トレーニングの継続と、微妙な体の使い方を積み重ねることが到達の鍵になります。
級ごとの到達に必要な練習時間と頻度

ここでは各級に到達するための練習頻度、1セッションごとの理想的な時間、目安となる到達月数、休息と回復の考え方をわかりやすく整理します。
練習頻度
練習頻度は現在の実力と目標級に合わせて設定することが大切です。
少ない頻度でも確実に成長できますが、継続性と強度のバランスが重要です。
- 週1回:ライトな維持と趣味レベル
- 週2回:10級〜8級を目指す初級者向け
- 週3回:7級〜5級を目指す中級者向け
- 週4回以上:4級以上を目指す競技志向または短期上達向け
週の合計回数だけでなく、連続して登る日と休む日の配分が成果に影響します。
1セッションの時間
1回のセッションは質が肝心で、長時間ただ登るだけでは効率が悪くなります。
目安として週1〜2回の人は60分から90分を基本にすると良いです。
週3回以上登る人は90分から120分を目安に、強度を分けると効率が上がります。
セッション構成はウォームアップ、メイン練習、クールダウンの順が基本です。
ウォームアップは軽いランジやフットワーク練習を含めて15分から20分を確保してください。
メイン練習は課題で追い込む時間と、ムーブ練習や足使いドリルを組み合わせると効果的です。
強度を上げる日はセット数を減らし、難しい課題にチャレンジする時間を多めに確保します。
低強度の日はムーブの反復や持久力を伸ばすトレーニングに充てると疲労管理がしやすいです。
クールダウンはストレッチと軽い有酸素を含めて10分程度を目安にしてください。
到達までの月数目安
下表は一般的な目安で、個人差やトレーニングの質で大きく変わります。
| 目標級 | 目安(月) | 必要な重点 |
|---|---|---|
| 10級〜8級 | 1〜3 | 基本の保持 バランス感覚 |
| 7級〜5級 | 3〜6 | フットワーク 体幹強化 |
| 4級〜2級 | 6〜18 | 指力向上 テクニック精度 |
| 1級〜初段 | 12〜36 | パワー系ムーブ習得 プロジェクト力 |
| 二段以上 | 24〜60 | 高度なムーブ習熟 総合的な強化 |
短期間で大きく伸ばすには、頻度を上げつつ回復をきちんと取ることが必要です。
休息と回復の目安
休息は努力と同じくらい重要で、筋肉と腱を回復させないと成長が停滞します。
一般的に高強度セッションの翌日は完全休養か軽いアクティブレストを推奨します。
週に1回は低負荷での登攀やストレッチに専念する日を設けると怪我予防につながります。
指や前腕の疲労が残る場合は、トレーニング量を減らすかデロード週を挟んでください。
デロード週はボリュームを50%程度に落とすか、難易度を下げてフォーム確認に充てます。
睡眠と栄養は回復の基礎です、タンパク質と良質な睡眠時間を確保してください。
痛みが続く場合は無理をせず、専門家に相談することをおすすめします。
級別に効くトレーニングメニュー

ここでは各級に効果的な練習内容を具体的にご紹介します。
初心者から上級者まで、目的に合わせた負荷と頻度のヒントを盛り込みました。
10級向け練習
10級はボルダリングを楽しみながら基礎を身に付ける段階です。
まずは足使いとバランスを優先して練習してください。
ホールドに頼りすぎない登り方や、体重移動の感覚を掴むことが重要です。
- 低めのトラバースでのフットワーク練習
- 片足立ちでのバランス保持練習
- ホールドの触り分け練習
- やさしいスラブでの体重移動トレーニング
セッションは無理をしない範囲で短めに繰り返すのがおすすめです。
7級向け練習
7級は動きの精度と簡単なテクニックが求められる段階です。
ルートを読む力とポジショニングを意識した練習を増やしてください。
具体的にはサイドホールドの使い方やヒールフック、トゥフックの導入が有効です。
ムーブを分解して反復することで、無駄な力を使わない登りを身に付けられます。
5級向け練習
5級では力と持久力の両方が問われますので、負荷を上げたメニューが必要です。
短めの限界トライと、複数課題を続けるサーキットを組み合わせて行ってください。
コアトレーニングと前腕の耐久性を高めるメニューを並行するのが効果的です。
動きの質を落とさずに回数をこなす練習を行って、実戦での安定感を養いましょう。
1級向け練習
1級は高度な技術と高いパワー持久力を要求されるレベルです。
計画的なトレーニングで強度と回復を両立させることが重要です。
| トレーニング項目 | 頻度目安 | 目標時間 |
|---|---|---|
| パワームーブドリル | 週2回 | 30分 |
| パワーエンデュランスサーキット | 週1回 | 40分 |
| 部分的な指力トレーニング | 週2回 | 20分 |
| ムーブ解析とクリップ練習 | 週1回 | 30分 |
テクニック練習と筋力練習を切り替え、疲労が残る日は強度を落とすと良いです。
トレーニングは継続が鍵ですので、計画を立てて無理なく進めてください。
ジム設定と外岩で生じる級差の要因

ジムの人工壁と外岩では、同じ級数でも体感する難易度が大きく変わることがよくあります。
要因を理解すると、練習の方向性が明確になり、外岩でのギャップを小さくできます。
ホールド形状差
ホールドの形状や素材感は、級差を生む最も分かりやすい要因です。
ジムでは均一に成型されたホールドが多く、グリップの取りやすさが保たれています。
外岩は天然の凹凸や欠けがそのままホールドになり、微妙な効き方の違いが登りを左右します。
- ポケット
- エッジ
- スローパー
- サムホールド
- フリクションの高い面
同じ「ポケット」でも形が違えば持ち方や力の入れ方が変わり、それが級差につながります。
壁傾斜差
壁の傾斜はムーブの種類を決め、使う筋肉や休め方に直結します。
| 傾斜 | 登り方のポイント |
|---|---|
| 垂壁 | 正確な足置き |
| 立ち気味 | 体重移動とフットワーク |
| やや斜め | バランスとレスト |
| オーバーハング | 上半身の引き付け |
ジムは一定の角度で練習しやすい反面、外岩では細かく角度が変化し、予想外の体勢を要求されます。
課題作成者差
セッターの好みや経験で課題の傾向は大きく変わります。
テクニック重視の設定だとムーブの精度が必要になり、パワー重視だと保持力が問われます。
外岩はラインの取り方や自然の形状を生かすため、セッターの意図以上にムーブが多様になります。
テープ運用差
ジムではテープやスタート位置のルールで課題の範囲が明示されます。
同じホールド群でもテープの範囲次第で易しくも難しくもなり、級の感じ方が変わります。
外岩は基本的にホールドやラインの指定が曖昧で、解釈の違いが生じやすいです。
競技志向のジムではルールが厳密で、級の再現性が高くなる傾向があります。
次の目標級を決める実践的な優先順位

次の目標級を決める際は、現在の実力と練習頻度を基準に、優先順位を付けると効率的です。
まず到達可能な範囲の目標を第一候補にし、次に技術と体力のどちらを伸ばすかで絞り込みます。
楽しさと達成感も重要で、苦手克服ばかりに偏ると継続が難しくなる場合があります。
短期目標は1〜2か月、長期目標は半年を目安にして、進捗を定期的に見直してください。
優先順位は柔軟に変えて、失敗から学び次の目標に反映させることを忘れないでください。

