これからボルダリングを始める方なら、シューズ選びでサイズやフィットに迷って不安になったことがあるはずです。
初心者がよく陥るのは試着不足や足幅無視、ソール硬度の誤選択で「痛い」「滑る」「疲れる」といった失敗に繋がる点です。
本記事では来店前準備から実寸測定、タイプ別の特徴、ジムや外岩ごとの選び方まで、失敗しない手順を具体的に解説します。
数値の測り方や推奨サイズ、つま先余裕の基準、試着時のチェック項目やレンタル活用法など、すぐ実践できる情報を中心にまとめました。
結論を急がず段階を踏んで選べば快適で長持ちする一足が見つかります。
まずは来店前準備から順に読み進めて、自分に合う一足を見つけましょう。
ボルダリングシューズを初心者が失敗せずに選ぶ手順

初めてボルダリングシューズを買うときは、サイズ感や用途を整理してから店に行くと失敗を防げます。
ここでは来店前の準備から試着、レンタルの活用まで、初心者が迷わない手順を順を追って説明します。
来店前準備
来店は夕方から夜にかけてがおすすめです、足は一日の中で少しむくむため、より実戦に近いサイズがわかります。
普段履いている靴下や、ボルダリングで使う予定の厚さのソックスを持参してください。
気になるモデルを事前にウェブで調べて、試したい候補を3つ程度に絞っておくと時間を有効に使えます。
実寸測定
必ず両足を測定して、長さと左右差を確認してください。
床に紙を置き、かかとをしっかり付けて立ち、つま先の先端を鉛筆でなぞる方法が簡単です。
測った長さは靴下を着用した状態での数値にしておくと、試着時の誤差を減らせます。
足幅確認
足幅はボルダリングシューズの快適さを左右しますので、測定だけでなく実際に履いて確認することが重要です。
足の甲や小指付け根あたりに痛みや圧迫感が出ないか、試着中に何度も足を動かして確かめてください。
幅広の方はワイド設計やローボリュームを選ぶと合いやすく、逆に幅狭の方はスリムなラストが向きます。
ソール硬度確認
ソールの硬さは感覚とパワーの伝達に直結します、柔らかめは足先の感覚を優先し、硬めはエッジでの安定感を出します。
ここでは代表的な硬度の違いを簡潔にまとめます、あなたのクライミングスタイルで選んでください。
| 硬度 | 特徴 | 向く用途 |
|---|---|---|
| 柔らかめ | 高感度 つま先ホールドにフィット |
複雑な足使い ボルダリングでの小さなホールド |
| 中間 | バランス型 感覚と安定の中間 |
ジム全般 初級から中級の練習 |
| 硬め | エッジ性能重視 踏み込みに強い |
長いルート 外岩でのスタンス利用 |
留め具選び
留め具には種類ごとに長所と短所があります、自分の通うジムや履き替え頻度に合わせて選んでください。
- ベルクロ 素早い着脱が可能 調整が簡単
- シューレース 細かいフィット調整が可能 高いフィット感
- スリッポン 装着が楽 緩みやすい場合がある
頻繁に履き替える方や短時間で何度も脱ぎ履きする方はベルクロが便利です。
フィット重視で長時間使う予定の方はシューレースが向いています。
試着チェック
試着は必ず両足で行い、実際に壁に立ってつま先で踏む動作を再現してください。
つま先の余裕、かかとのフィット感、足の裏全体の密着感を重点的に確認してください。
店員さんにアドバイスを求めて、異なるサイズやモデルを比較試着することをおすすめします。
痛みがある場合はサイズを下げるべきではないことを覚えておくと安心です。
レンタル活用
最初はレンタルで複数のモデルを試すと、自分に合うタイプが早く見つかります。
レンタルで試して良かったモデルを基準に購入候補を絞ると失敗が少なくなります。
ただしレンタルはモデルやサイズが限られるため、最終的には実店舗での試着を推奨します。
タイプ別の特徴と用途

ボルダリングシューズには形状と容量の違いで得意分野が分かれます。
ここでは代表的な6タイプをわかりやすく解説します。
フラット
フラットタイプは靴底の形がほぼ平らで、つま先に過度な圧力がかからない設計です。
つま先に余裕があるため、歩行や長時間の使用で疲れにくい特徴があります。
初心者やエントリーユーザーが最初に選びやすいタイプで、トレーニングやルートクライミングに向いています。
弱点としては、垂直〜強傾斜でのつま先精度が劣る点があるため、難しいボルダー課題には不向きです。
ニュートラル
ニュートラルはフラットとややダウントゥの中間に位置するオールラウンダーです。
適度なつま先のホールド感と疲れにくさを両立しているため、長めのルートに向いています。
ビギナーから中級者まで幅広く使える安定感が魅力で、一本で用途をカバーしたい方におすすめです。
ダウントゥ
ダウントゥはつま先が下方向に湾曲しており、つま先に力を集めやすい形状です。
小さなエッジやポケットに対する立ち込みが強く、オーバーハングやテクニカルな課題で真価を発揮します。
ただし、長時間履くとつま先への負担が増えるため、慣れるまでは短時間のトライがお勧めです。
アグレッシブ
アグレッシブは強いダウントゥとアシンメトリーを持つ競技向けシューズです。
つま先集中型の力の伝達が非常に高く、短時間の高難度ボルダーに最適です。
- 短い強傾斜の課題
- 精密なつま先フック
- 高難度の一手勝負
しかし、足への圧迫が強く、長いルートや長時間の使用には向きませんので注意が必要です。
ハイボリューム
ハイボリュームはつま先や甲周りに余裕がある設計で、幅広や甲高の足型に合いやすいです。
長時間のルートや外岩での安定性を重視するクライマーに向いています。
| 項目 | ハイボリューム | ローボリューム |
|---|---|---|
| 特徴 | 余裕のあるつま先 厚めの靴幅 |
細身のつま先 タイトなフィット |
| 向く用途 | 長時間のルート 外岩での快適性 |
短時間の高強度課題 精密な足置き |
購入時は自分の足のボリュームと靴のフィット感をよく確認して選ぶと失敗が少ないです。
ローボリューム
ローボリュームは細身でつま先や甲が薄く設計され、足に吸い付くようにフィットします。
つま先の感覚が鋭く、精密な足技や小さなエッジに強いのが利点です。
しかし足幅が広い方には痛みやサイズ不足が起きやすいので、試着での確認とサイズ調整が重要です。
サイズ選びの具体的な数値と測り方

ボルダリングシューズのサイズ選びは感覚だけで決めないことが重要です。
実寸と用途を照らし合わせることで、後悔しない一足に近づけます。
実寸測定法
まず自宅で正確に足の実寸を測る方法を説明します。
床に紙を敷き、かかとを壁につけて立ちます。
- かかとを壁に密着
- 床に紙を敷く
- 足の最長部に印をつける
- 印からかかとまでを定規で測る
足の長さは立った状態で測ることがポイントです。
座ったまま測ると体重がかからず、実際のサイズより短く出る傾向があります。
両足は微妙に長さが違うことが多いので、左右とも測った上で長い方を基準にしてください。
推奨サイズ目安(cm)
一般的な目安を表にまとめましたので、測定値と照らし合わせてみてください。
| 足長 | 推奨シューズ内長差 |
|---|---|
| 22cm | 0.5cm |
| 23cm | 0.5cm |
| 24cm | 0.8cm |
| 25cm以上 | 1.0cm前後 |
表はあくまで目安であり、ブランドやモデルによって差があります。
幅のある足や甲の高い方は、内長差を少し増やす調整が必要になることが多いです。
つま先余裕基準
つま先の余裕は一般的に0.5mmから5mmの範囲を目安にしてください。
初心者は無理に攻めすぎず、およそ3mm前後を目安にすると違和感が少ないです。
競技志向で小さく履く場合は0mmから2mmまで詰める方もいますが、長時間の使用で痛みが出やすくなります。
つま先が完全に押しつぶされる感覚は避けるべきです。
また、形状がダウントゥやアグレッシブなモデルはつま先圧が強くなるため、余裕を少なめにするかサイズをワンサイズ上げる検討が必要です。
試着時間目安
試着は短時間で終わらせず、少なくとも10分以上履いて確認することをおすすめします。
最初の5分は足が馴染む時間ですから、その後につま先やかかとの当たりをチェックしてください。
ジムで実際に壁を数本登ってみると、ホールドでのフィーリングが分かりやすくなります。
長時間の試着は靴を痛めるため、30分を超える試着は避けると良いです。
購入前に家での慣らし履きを想定して、試着時に動きを確認しておくと安心です。
ジム・外岩別の選び方

ジムと外岩では求められる性能が変わるため、シューズ選びの優先順位も変わります。
ここではボルダーとロープ、スポートとマルチピッチでの選び方を具体的に説明します。
ジム(ボルダー)
ボルダーは短時間の力勝負が多く、足先の精度と足裏感覚が重要になります。
そのため、つま先のフィット感を重視し、ダウントゥやアグレッシブ寄りのシューズが有利です。
ただし、初めてであれば極端に小さいサイズは避け、痛みで登りが崩れない範囲に留めると良いです。
ヒールフックやトゥフックを多用するルートがある場合は、ヒールのホールド感もチェックしてください。
- タイトなフィット
- 敏感なソール
- 強いダウントゥ
- しっかりしたヒールカップ
ジム(トップロープ)
トップロープは持久力が求められることが多く、快適性と疲労の少なさが重要です。
ニュートラル〜フラット寄りのシューズで、ほどよい剛性があるものを選ぶと長時間のルートに向きます。
サイズはボルダーより若干余裕を持たせても問題なく、つま先の痛みでフォームが崩れないことを優先してください。
外岩(スポート)
外岩のスポートクライミングでは、岩質に合わせたゴムの耐久性とエッジング性能が必須です。
小さなポケットやエッジを使う機会が多ければ、感度とフリクションの高いソールが役に立ちます。
また、外岩では傷や摩耗が早いので、補修のしやすさやソール厚もチェックポイントになります。
| 状況 | おすすめタイプ | 特長 |
|---|---|---|
| 小さなホールド | 敏感なソール | 感度重視 |
| 滑りやすい岩 | フリクション重視 | 粘りのあるゴム |
| 長時間のルート | 快適性重視 | 適度な剛性 |
外岩(マルチピッチ)
マルチピッチでは長時間の装着となるため、快適性と耐久性を最優先にしてください。
ラストのボリュームが高めで、通気性や締め付け調整がしやすいレースアップタイプが向いています。
また、アプローチの歩行を考えると、ソールの剛性と耐摩耗性も重要な選択基準になります。
初心者がモデルを絞るためのチェック項目
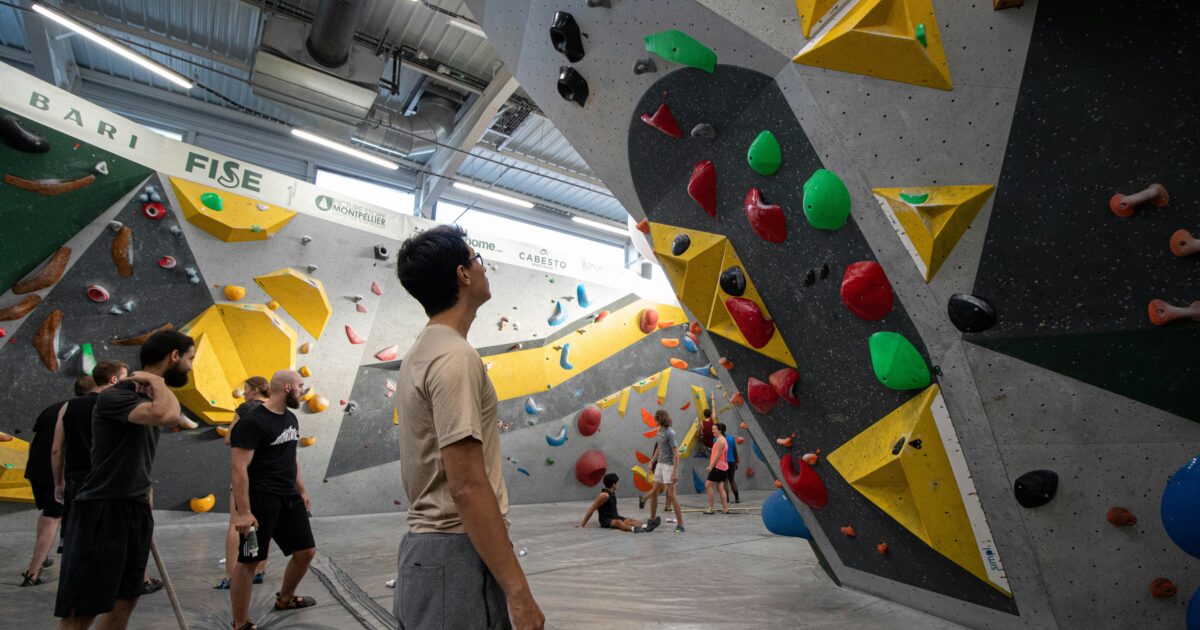
ボルダリングシューズ選びで失敗を避けるには、まず目的と予算を明確にすることが大切です。
用途に合った特徴を把握すると、試着時間が短縮でき、満足度の高い一足に出会いやすくなります。
エントリーモデル特徴
エントリーモデルは履き心地を重視した設計が多く、初めてでも違和感が少ないのが魅力です。
ラストはフラット寄りかニュートラルが中心で、ダウントゥやアグレッシブな形状はあまり使われません。
ラバーは中庸の硬さで、足先にかかるストレスが抑えられている製品が多いです。
通気や脱ぎ履きのしやすさにも配慮されていて、長時間のジム通いにも向いています。
性能面では高性能モデルに及ばない部分もありますが、コストパフォーマンスが高く、まずはここから試すのがおすすめです。
価格帯判断
価格から絞るとモデルの狙いが明確になります、予算に応じて必要な性能を優先しましょう。
- 8000円以下 エントリー向け
- 8000〜15000円 コスパ重視
- 15000〜25000円 中級者向け性能あり
- 25000円以上 ハイエンドモデル
安価なモデルは手軽に始められます、性能や耐久性が必要なら中価格帯を検討してください。
耐久性確認
耐久性は長く使うための重要な要素で、ソールやランの作りをチェックしてください。
| 確認項目 | 具体例 |
|---|---|
| ソール厚さ | 3mm 4mm 4.5mm |
| ラバー種類 | スタンダード ラバー高性能 |
| 縫製と接着 | 二重縫製 力強い接着 |
| 補修性 | リソール対応 交換パーツあり |
ソールが薄いほど感覚は良くなりますが、消耗が早くなる点に注意が必要です。
縫製がしっかりしているか、接着剤のはみ出しなどで耐久性を判断してください。
交換保証確認
購入前に試着や交換ポリシーを確認すると安心です。
メーカーやショップによっては初期不良やサイズ交換の期間を設けていることがあります。
リソール対応や有償での修理サービスがあるかも重要な判断材料です。
レシートや保証書の保管方法も確認して、万が一の際に手続きできるようにしておきましょう。
購入後の手入れと買い替えサイン

購入後の手入れは、シューズの寿命と快適性を左右します。
使用後は布で泥やチョークを落とし、湿気は風通しの良い場所で自然乾燥することをおすすめします。
直射日光やストーブの近くでの乾燥は避けてください。
内部のにおい対策には吸湿剤や新聞紙が有効で、定期的に取り替えて保管してください。
本革製は専用クリームで手入れし、洗濯機での丸洗いは避けた方が良いです。
頻繁に使う場合は複数足をローテーションし、ソールの摩耗は早めにリソールを検討すると長持ちします。
買い替えのサインはソールの著しい薄さ、ラバーとアッパーの剥離、ミッドソールの沈み込みなどです。
目安として週に数回使う方は半年〜一年で点検し、ライトユーザーなら1〜2年での見直しをおすすめします。
適切な手入れと早めの判断で、パフォーマンスを維持しつつコストを抑えて長く使うことができます。

